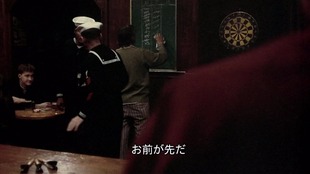さらば冬のかもめ

アメリカ映画におけるダーツのイメージ
あくまでも個人的でおおよそ適当なイメージだけれども、アメリカ(ハリウッド)映画を観ていると、ダーツマシンが映り込む場面に気付きやすい。
そのうちの多くは、大体こういう店でのシーンだと思っていた。
・街の外れのバー
外観には、アメリカンバイクやアメ車がずらりと並んでいる。
・店の中
中央にはビリヤードの台が並び、壁際を見ると、電飾キラキラ系のピンボールやジュークボックス、スロットマシン、そしてたまにダーツマシンが置いてある。
・店のカウンター
革ジャンを羽織った髭面のチョイ悪、というか、極悪な風体のいかついオヤジ共がジョッキをうぐうぐと呷っている。
・BGM
へヴィメタ及びデスメタルなどの類の禍々しい音楽。
映画の主人公は、このような店を訪れ、カウンターのオヤジたちに「おウチへ帰んな、ボウヤ」とか言われて、いざ乱闘が始まるのである。
実際にダーツを投げる場面なんかは、ほとんど、いや、まったくない。
あくまでも景色の一部、インテリアとしてのダーツマシンがそこには存在するだけなのだ。
『さらば冬のかもめ』とダーツ
『さらば冬のかもめ』
1973年にアメリカで製作されたこの作品。
ベテラン海軍下仕官のバダスキー(ジャック・ニコルソン)と同僚のマルホールの二人が、ちんけな窃盗を働いて8年の懲役を食らった新兵のメドウズ君をアメリカのノーフォークからポーツマスへ護送する、という物語。
目的地へ向かう。
ただそれだけのロードムービーの秀作。
内容についての考察は他の専門の方々が散々やっているのでここでは割愛しますが、物語の途中、三人は、世界一うまいビール(ハイネケン)を飲もうとバーへ向かう。
そして、ダーツを投げる場面へと至るのである。
ビールの話はそっちのけ。
バダスキー役のジャック・ニコルソンはとにかくダーツを投げている。
やがて、他のお客さんに賭けダーツを挑み、なんとあっさり大勝ちし、60 ドルほど儲かって三人で山分けする。
ウソだろ……ウソですよ、大嘘、映画のウソ。
スティールティップダーツの難しさをボクは良く知ってますよ。
そんな簡単に勝てるわけないよ、フィル・テイラーかよ。
と、そこまで観ていて、ふと疑問が湧いた。
あれ、何故ダーツマシンではなく、ブリッスルボードなんだ? と。
ダーツマシンの出自
スティールダーツ(スティールティップポイントダーツ)とは先端が金属の針になっているダーツのこと。
ブリッスルボードという麻を圧縮したボード(木製や紙製のボードもある)に刺して遊びます。
点数の計算も自動ではありません。
映画に登場したのは何故このスティールダーツだったのか。
それもそのはず。
現在の形のようなダーツマシンが初めて開発されたのは1980年代。
アメリカのメダリスト社というところが最初に作ったのですが、その後、日本へもマシンが輸入され、現在のような爆発的な広がりを見せるわけです。
この映画が製作されたのは1973年なので、同年代を舞台としているならば、当然ダーツマシンはまだ存在していない。
この映画にスティールダーツが登場したのは必然だったのです。
なるほど。
今後は、思い込みによる『アメリカ映画=ダーツマシン』のイメージは改めなければなりません。
1980年代より前の時代設定の作品に、ダーツマシンは出てこないのだ、と。
もし出てきたら、製作者側のミス、ということにしておきましょう。
さて、この映画、ダーツばかりの映画ではありません。
どうぞダーツを抜きにして映画の内容を存分にお楽しみください。
最後に一言。
賭けダーツはダメ、絶対(一応)。